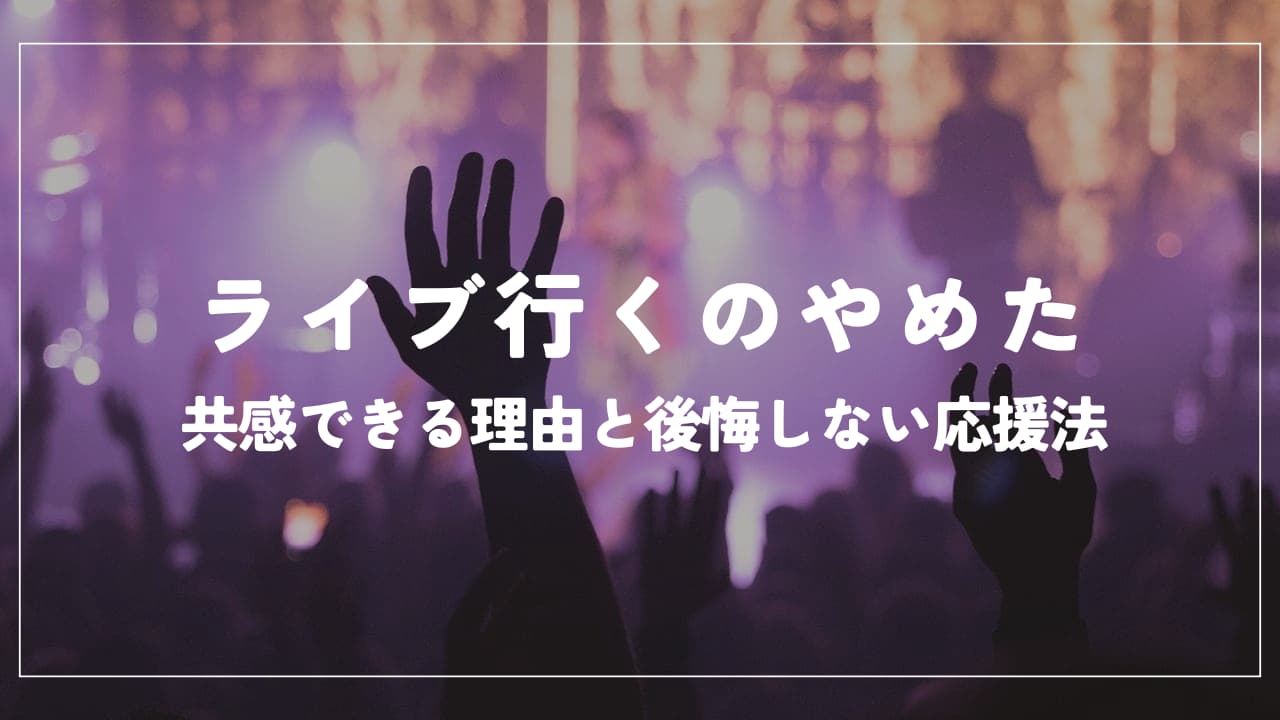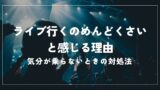かつてはあれほど楽しみにしていた推しのライブ。
しかし、気づけば「ライブ行くのやめたい」と感じている方もいるのではないでしょうか。
「ライブ行くのめんどくさい」「なんだか気分が乗らない」と感じたり、経済的な負担や体力の問題を実感したり。
あるいは、チケット争奪戦のストレスや、周りの環境の変化が影響しているのかもしれません。
「チケット買ったけどやっぱり行かない場合、どうすればいいの?」「空席にするとペナルティはある?」そんな疑問を抱えている人も少なくないはずです。
「行かない方がいいのか」「行かないと後悔するのか」と迷い、ライブに行く価値そのものを見つめ直している人もいるでしょう。
この記事では、ライブに行かなくなった理由や背景を徹底解説し、行くか迷うときの判断基準や、ライブに行かなくても推し活を楽しむ方法を紹介します。
ライブ行くのやめたとしても、応援する気持ちがなくなったわけではないはずです。
この記事を読めば、気持ちを整理し、自分に合った応援スタイルを見つけるためのヒントが得られるでしょう。
なぜライブ行くのやめたのか?その背景にある理由
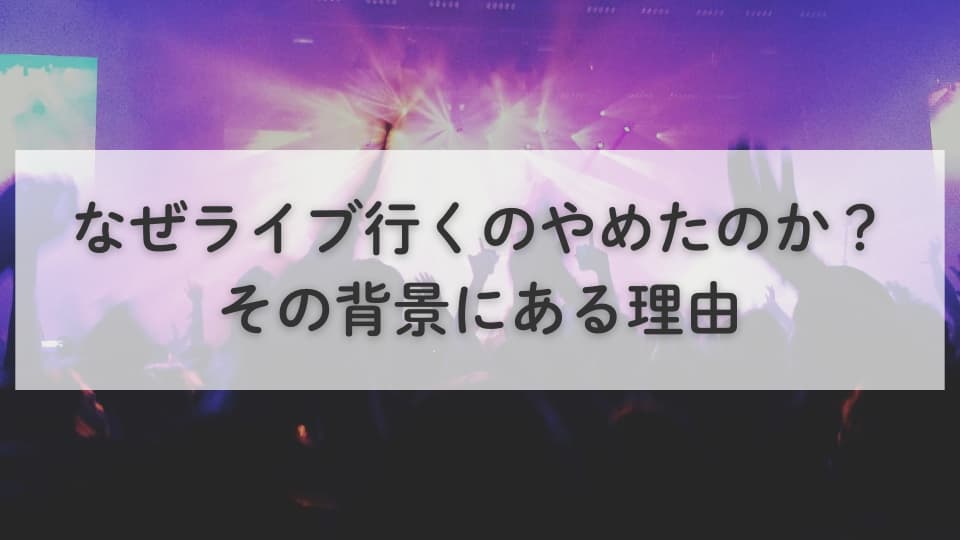
推し活を続けるうちに、ライブやコンサートへの参加を徐々に減らしていく人は少なくありません。
かつては何としてでも行きたかったライブが、いつの間にか「行かなくても良いかな」と思うようになる心理的変化には、さまざまな要因が絡み合っています。
ここでは、ライブ行くのやめた背景にある様々な理由を探っていきます。
- ライブに行かなくなった理由
- ライブ行くのめんどくさいと感じている人は意外と多い?
- 行くか迷う場合:行かないと後悔するライブは?
- チケット買ったけどやっぱり行かない場合の対処法
- ライブに行かないで空席にするとペナルティがある?
- ライブに誘われたけど気分が乗らない時の断り方
ライブに行かなくなった理由
「ライブに行かなくなった」と一言で言っても、その背景には十人十色の理由が存在します。
そこで、よく聞かれる代表的な理由をいくつか掘り下げてみましょう。
ご自身の状況と照らし合わせながら読み進めてみてください。
経済的な負担
ライブに参加するには、想像以上にお金がかかるものです。
まず、チケット代そのものが高騰している傾向が見られます。
人気のアーティストともなれば、1万円を超えることも珍しくありません。
それに加えて、ライブが遠方で行われる場合、会場までの交通費や宿泊費も大きな負担となります。
さらに、ライブでは限定グッズが販売されることが多く、「今しか買えない」という心理から予定外の出費につながりやすいです。
グッズを全て揃えようとすると、1回のライブで数万円の出費は当たり前です。
こうした経済的な負担が積み重なり、ライブへの参加をためらうようになるケースは少なくありません。
体力や集中力の低下
ライブは楽しい一方で、体力的な消耗も激しいイベントです。
開演前には長時間並んだり、開演中はずっと立ちっぱなしだったりすることも多いです。
特にオールスタンディングのライブでは、人口密度も高く、周りの熱気も相まって想像以上に疲れます。
また、大音量の音楽や照明、周囲の歓声など、強い刺激に長時間さらされるため、集中力を保つのも大変です。
以前は平気だったはずなのに、年齢を重ねるにつれて、ライブ後にどっと疲れが出たり、翌日まで響いたりするようになったと感じる方もいるでしょう。
体力や集中力の低下を自覚すると、「無理してまで行くのは…」と考えてしまうのも無理はありません。
チケット争奪戦のストレス
人気アーティストのライブチケットは、まさに争奪戦です。
人気公演では抽選販売が主流となっていますが、ファンクラブに入っていても、倍率が高く、連続で落選することも少なくありません。
何度も希望を持って申し込み、その度に落選通知を受け取る精神的ダメージは小さくありません。
「もう応募するのも疲れた」「当たる気がしない」という諦めの気持ちから、チケット申し込み自体をしなくなる人もいます。
転売問題や多名義問題も深刻で、正規のルートで入手できない悔しさや、ルールを守っている人が損をする不公平感もストレスの一因です。
こうしたチケット入手の困難さが、ライブへの意欲を削いでしまうことがあります。
ファンのマナー違反や会場の雰囲気の変化
残念なことですが、一部のファンのマナー違反が、ライブを楽しむ気持ちを萎えさせてしまうこともあります。
列の割り込みや過度な声援、周囲の視界の妨げなど、他の人の迷惑を考えない自分勝手な行動などは、せっかくの楽しい時間を台無しにしてしまいます。
また、ファン層の変化や時代の流れとともに、ライブ会場の雰囲気が変わったと感じる古参ファンも少なくありません。
昔ながらの楽しみ方がしにくくなったり、新しいノリについていけなかったりすると、居心地の悪さを感じることもあるでしょう。
自分が心地よいと感じられる空間でなくなった場合、自然と足が遠のいてしまうのは仕方ないことです。
ライフステージの変化
人生には様々な転機が訪れます。
就職、転職、転勤、結婚、出産、育児、介護など、ライフステージが変わると、生活の優先順位も大きく変化します。
以前は自由に使えていた時間やお金が、仕事や家庭のために必要になることは自然な流れです。
特に、子育てや介護など、自分の都合だけでは動けない状況になると、ライブのために家を空けること自体が難しくなります。
時間的、物理的な制約が増えることで、ライブへの参加を断念せざるを得なくなるケースは非常に多いです。
これは決してネガティブな理由ではなく、生活の変化に伴う自然な選択と言えるでしょう。
一緒に行く人がいなくなった
かつては一緒にライブを楽しんでいた友人や仲間が、それぞれの事情で一緒にライブへ行けなくなることは珍しくありません。
友人が転居したり、結婚や出産を経て家庭を優先するようになったり、あるいは他のアーティストに興味が移ったりと、理由は様々です。
もちろん、一緒に行く人がいなくても、一人でライブに参加する人は多いです。
しかし、以前は友人と一緒に楽しんでいた人にとって、一人での参加はハードルが高く感じられることがあります。
開演前の長い待ち時間を一人で過ごすことや、ライブが終わった直後の興奮や感想をすぐに共有できないことに、物足りなさや孤独を感じることもあるでしょう。
そうした気持ちが積み重なり、次第にライブから足が遠のいてしまう人もいるのです。
推しへの熱量の変化
推しへの熱量は、常に一定とは限りません。
時間の経過とともに、興味の対象が変わったり、以前ほど情熱を注げなくなったりすることは、誰にでも起こり得ることです。
他に夢中になれる趣味が見つかったり、仕事や学業に集中したい時期が来たりすることもあるでしょう。
推しへの気持ちが完全に冷めたわけではなくても、「以前ほど必死にチケットを取ってまで行きたいとは思わない」という温度感になることもあります。
熱量の変化は、ごく自然な心の動きです。
無理に以前と同じ熱量を維持しようとする必要はなく、自分の気持ちの変化を受け入れることも大切です。
ライブ行くのめんどくさいと感じている人は意外と多い?
ライブは特別な体験ですが、その準備や当日のことを考えると「めんどくさい」と感じてしまう瞬間があるのも事実です。
チケットの手配から始まり、当日の服装選び、会場までの移動手段の確認、持ち物の準備など、意外と手間がかかります。
会場に着いてからも、入場待機列、グッズ購入列、トイレ列など、何かと待つ場面が多いです。
人混みが苦手な人にとっては、それだけで疲れてしまうかもしれません。
ライブ後の混雑した帰り道や、翌日の疲労感を想像すると、家でゆっくり音楽を聴いたり、配信を見たりする方が楽だと感じてしまう人もいるでしょう。
SNSなどを見ていても、「ライブ行きたいけど、遠征が面倒」「人混みを考えると億劫」といった声は意外と多く見られます。
決して特別な感情ではなく、多くの人が共感できる感覚と言えるかもしれません。
行くか迷う場合:行かないと後悔するライブは?
ライブに行くかどうか迷った時、「行かなかったら後悔するかも」という気持ちがよぎることがあります。
もちろん、全てのライブに行く必要はありませんが、中には後で「やっぱり行っておけばよかった」と感じやすいタイプのライブも存在します。
例えば、以下のようなライブは、行かないと後悔する可能性が比較的高いかもしれません。
- アーティストの解散・活動休止・引退前のライブ
- メンバーの卒業・脱退が発表されているライブ
- 周年記念ライブや特別な企画ライブ
- 特別な会場でのライブ
- 自分が特に思い入れのある楽曲が披露されるライブ
- 海外アーティストの来日公演
結局のところ、「行かないと後悔するライブ」は人それぞれですが、「二度とない機会」と感じるライブは、多少の労力や費用をかけても参加する価値があります。
もちろん、上記に当てはまらなくても、自分の直感が「これは行くべきだ!」と告げている場合は、その感覚を信じるのも一つの手です。
最終的には、自分の気持ちと、時間的・経済的な状況などを総合的に判断することが重要です。
チケット買ったけどやっぱり行かない場合の対処法
せっかくチケットを手に入れたのに、急な体調不良や外せない用事、あるいは単に気分が変わって「やっぱり行けない」「行きたくない」となることもあり得ます。
そんな時、手元のチケットをどうすれば良いか迷うかもしれません。
通常のチケットは購入後のキャンセル・返金が認められていないケースが多いです。
最も推奨される方法は、公式のリセールサービスの利用です。
近年、多くの興行主やプレイガイドが、チケットを定価で再販できる公式の仕組みを導入しています。
これを利用すれば、ルールに則った形で他のファンにチケットを譲ることができます。
また、信頼できる友人や知人への譲渡も一つの選択肢です。
ただし、チケットによっては、譲渡が禁止されている場合や、入場時に本人確認が必要な場合もあるため注意が必要です。
違反すると、入場を拒否されるだけでなく、今後チケットが取れなくなる可能性があります。
必ず事前に公式サイトの注意事項を確認してください。
絶対に避けるべきなのは、定価を超える価格での転売です。
これは法律で禁止されているだけでなく、アーティストや他のファン、そしてイベント業界全体に悪影響を与える行為です。
安易にSNSや転売サイトで高額転売することは絶対にやめましょう。
>>チケットの高額転売は禁止です!チケット不正転売禁止法|政府広報オンライン
ライブに行かないで空席にするとペナルティがある?
チケットのリセールができない場合や、譲渡が禁止されている場合は、諦めて空席にするのが安全です。
通常、チケットを購入し、支払いが完了していれば、ライブに行かないこと自体にペナルティはありません。
ただし、チケット代金の未払いによるキャンセルは、ペナルティが科されることがあるので注意が必要です。
当選後の未入金を繰り返していると、将来的にチケットの申し込みができなくなる可能性があります。
ライブに誘われたけど気分が乗らない時の断り方
友人や知人からライブに誘われたけれど、あまり興味がないアーティストだったり、その日は気分が乗らなかったりすることもあります。
そんな時、相手を傷つけずに上手に断るにはどうすれば良いでしょうか。
大切なのは、正直に、かつ丁寧に断ることです。
まず、誘ってくれたことへの感謝の気持ちを伝えましょう。
「誘ってくれてありがとう!すごく嬉しいんだけど…」といった前置きがあると、相手も悪い気はしません。
その上で、断る理由を正直に伝えるのが基本ですが、言い方には配慮が必要です。
「そのアーティストに全然興味ないんだよね」とストレートに言うのではなく、「最近忙しくて体力的にきつい」「金銭的にちょっと厳しくて…」など、相手を不快にさせない表現を選びましょう。
体調を理由にするのも一つの方法ですが、使いすぎると心配をかけてしまうかもしれません。
もし、そのアーティスト自体に興味がない場合は、「あまり詳しくなくて、せっかく誘ってくれたのに楽しめなかったら申し訳ないから」といった伝え方もできます。
断る際は、行けないという意思をはっきりと伝えることも大切です。
「行けたら行く」「考えておく」などの曖昧な返事は期待を持たせてしまいます。
ライブ行くのやめた後の推し活はどうする?
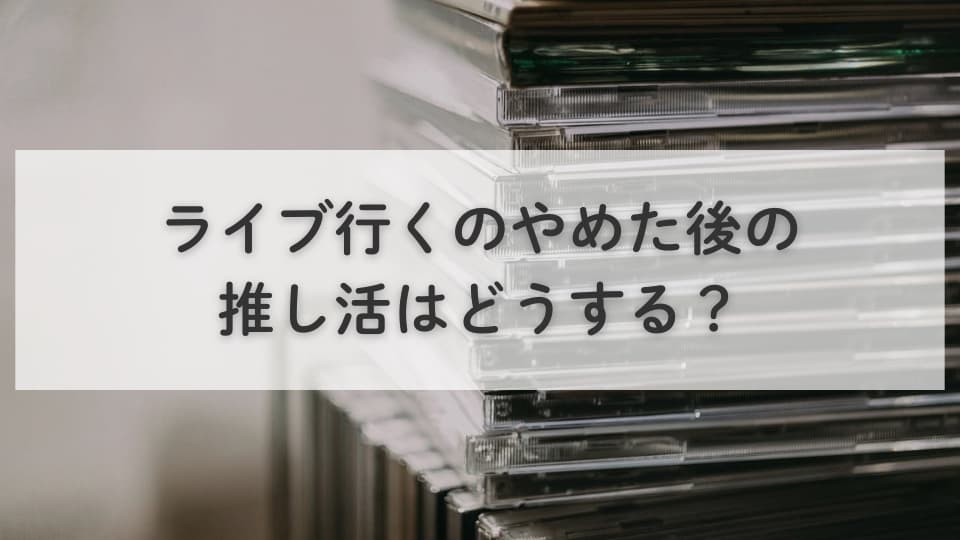
ライブに行かなくなったからといって、アーティストへの応援が終わるわけではありません。
推し活の形は多様化しており、ライブ会場に足を運ばなくても、様々な方法で愛情や応援の気持ちを表現することができます。
ここでは、ライブに行かない選択をした後も続けられる、推し活の具体的な形を見ていきましょう。
- ライブ以外での応援の形
- ライブは行かない方がいい?ライブに行く価値とは何なのか
ライブ以外での応援の形
ライブという「現場」に行かなくても、自宅や日常の中でできる応援はたくさんあります。
CDやグッズを購入したり、テレビや配信を視聴したり、SNSで情報を広めたりすることも、立派な応援活動です。
自分のペースで、無理なく続けられる方法を見つけることが大切です。
CD・Blu-ray・グッズを購入する
CDやBlu-ray・DVDといった音楽・映像作品の購入は、アーティストの活動を直接的に支える分かりやすい方法です。
売上枚数はアーティストの人気の指標となり、次の作品制作や活動の資金源にも繋がります。
手に取れる形で作品を持つことで、コレクションする楽しみもあります。
また、公式グッズの購入も同様に、アーティストや所属事務所の収益となります。
Tシャツやタオル、ポーチなど、日常で使えるアイテムを選べば、推しへの愛をアピールしつつ実用的に使用できるでしょう。
オンラインストアを利用すれば、会場に行かなくても手軽に購入可能です。
出演番組をリアタイ・配信で視聴する
応援しているアーティストがテレビ番組やラジオ番組に出演する場合、リアルタイムで視聴・聴取することは、視聴率や聴取率に貢献する形で応援になります。
これらの数字は、番組スポンサーやテレビ局・ラジオ局に対するアーティストの影響力を示す指標となり、今後のメディア露出にも繋がる可能性があります。
最近では、放送後に見逃し配信サービス(TVerなど)や、番組公式のYouTubeチャンネルで視聴できるケースも多いです。
配信での再生回数も重要な指標となるため、リアルタイムで見るだけでなく、配信でも視聴することでさらなる応援につながります。
サブスクや動画を再生する
SpotifyやApple Musicといった音楽ストリーミングサービス(サブスク)で楽曲を繰り返し聴くことも、有効な応援方法です。
再生回数は、アーティストの収益に直接繋がるだけでなく、ランキングや注目度にも影響を与えます。
プレイリストに入れて日常的に聴くだけでも、着実な応援となります。
また、YouTubeなどの動画プラットフォームで、ミュージックビデオや公式コンテンツを視聴することも同様です。
再生回数、高評価、コメント、共有といったアクションは、動画の評価を高め、より多くの人の目に触れる機会を増やすことに繋がります。
広告収益にも貢献できます。
SNSでいいね・拡散する
X(旧Twitter)、Instagram、TikTokなどのSNSを活用した応援も、手軽かつ効果的です。
「いいね」やリポスト(リツイート)など、アーティストの公式アカウントの投稿に積極的に反応することで、アルゴリズム上の表示優先度が上がります。
より多くの人の目に触れる可能性が高まり、アーティストの活動を知ってもらうきっかけを作れるでしょう。
また、ハッシュタグを活用した投稿も効果的です。
例えば、出演番組の感想などをハッシュタグをつけて投稿すると、トレンド入りなどの話題性を生み出し、番組を盛り上げられます。
アーティスト本人や番組スタッフの目に留まる可能性もあり、ポジティブな声援が番組作りのモチベーションにも繋がるでしょう。
出演CMの商品を購入する
応援しているアーティストが企業のCMに出演している場合、その商品やサービスを購入・利用することも応援になります。
CM起用の効果があったと企業側が判断すれば、契約継続や、他の企業からの新たなCM起用に繋がる可能性があります。
もちろん、無理に必要のないものを買う必要はありませんが、もし普段利用している商品や、興味のあるサービスであれば、積極的に選んでみるのも良いでしょう。
商品を購入した際に、SNSなどで「CMを見て買いました」と発信するのも、企業へのアピールになるかもしれません。
ファンクラブを継続する
ライブには行かなくなったとしても、ファンクラブの会員であり続けることも、応援の形の一つです。
ファンクラブの会費は、アーティストの活動資金を直接的に支える重要な要素です。
また、ファンクラブ会員でいることで、会員限定のコンテンツ(ブログ、動画、写真など)を楽しめたり、最新情報をいち早く受け取れたりするメリットもあります。
ライブに行かないという選択をしたとしても、ファンクラブを通じてアーティストとの繋がりを感じ続けたい、という気持ちがあるなら、継続する価値は十分にあると言えるでしょう。
ライブは行かない方がいい?ライブに行く価値とは何なのか
ライブに行くことの価値や意義について、改めて考えてみましょう。
ライブは決して「行かなければならないもの」ではなく、あくまで推し活の選択肢の一つです。
ライブに行くか行かないかは、個人の自由な選択であり、どちらが良い・悪いというものではありません。
ライブに行かない選択をしたとしても、罪悪感を感じる必要は全くありません。
前述の通り、応援の形は多様であり、自分に合った方法で推し活を楽しめば良いのです。
一方で、ライブには、他では得難い特別な価値があることも事実です。
- 生のパフォーマンスの迫力
- 会場の一体感
- ステージ演出の臨場感
- 非日常的な空間
- その日限りの特別なパフォーマンス
ライブの本質的価値は、「一期一会の体験」にあります。
同じセットリストでも、その日の空気感、観客の反応、アーティストのコンディションによって、二度と同じ体験はできません。
配信や円盤では味わえない「その場にいる実感」や「共有する高揚感」は、ライブならではの魅力です。
もし、経済的な理由や体力的な理由でライブから足が遠のいているけれど、心のどこかでは「また行きたいな」という気持ちがあるなら、無理のない範囲で参加できる方法を探ってみるのも良いかもしれません。
なぜライブ行くのやめたのか?:まとめ
今回の記事のまとめです。
ライブに行かなくなった理由は人それぞれですが、無理せず距離を取る選択も推し活の一つの形です。
経済的負担や体力の問題だけでなく、ライフスタイルや気持ちの変化によって決断する人も少なくありません。
ライブに行かないと決めた後も、応援の方法はたくさんあります。
CDやグッズの購入、配信視聴、SNSでの拡散など、できることから無理なく続けることが可能です。
ライブには他では得られない特別な価値があることも事実ですが、その価値の感じ方も人それぞれです。
現場に足を運ぶことだけがファンの証ではありません。
その時々の自分にとって最も心地よい応援の形を選びながら、長く推し活を楽しむことが大切です。
行くか迷っている場合は、その気持ちを否定せず、自分の今の状態をよく見つめることが鍵になります。
無理のない選択をしたその先に、また新しい推し活の楽しみ方が見えてくるはずです。